自閉症スペクトラム障害(ASD)のある子どもたちの中には、歩き方に独特の特徴が見られることがあります。これは単なる個性ではなく、脳や身体の発達に関連した要因が複雑に絡み合っている可能性があります。
モナシュ大学で神経発達障害を専門とするニコル・ラインハート教授は、自閉症と歩行の関係、そして必要な支援方法について詳しく解説しています。

👣自閉症に見られる特徴的な歩き方とは?
ラインハート教授によると、自閉症のある子どもたちには次のような歩行パターンが見られることがあります:
- つま先歩き(Toe Walking)
足の指の付け根で歩行する。 - 内旋歩行(In-Toeing)
両足または片足を内側に向けて歩く。 - 外旋歩行(Out-Toeing)
足が外側に開いた状態で歩く。
さらに、過去の研究から以下のような傾向も報告されています:
- 歩く速度が全体的に遅い
- 歩幅が広い
- 足が地面から離れている時間が長い
- 一歩ごとに時間がかかる
これらの特徴は個人差があり、自閉症のすべての人に当てはまるわけではありませんが、臨床評価の一環として歩行観察が役立つこともあります。

🧠「歩き方」は脳のどの部分と関係しているのか?
自閉症に関連する歩行の違いには、脳内の特定部位が深く関与していると考えられています。
大脳基底核
身体動作の順序づけを司り、滑らかな動きや姿勢の変化に必要不可欠な役割を果たします。ここに発達の遅れや機能の違いがあると、ぎこちない歩き方になりやすいとされます。
小脳
小脳は、視覚情報と身体の位置情報を統合してタイミングを調整し、姿勢を安定させます。自閉症の人ではこの機能がうまく働かないことがあり、バランスを取るのが難しくなることがあります。
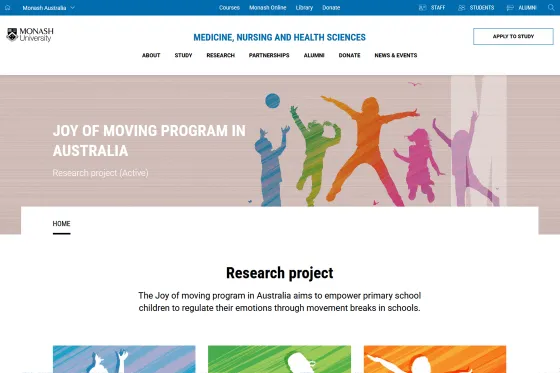
ラインハート教授は今後も研究を続け、子どもたちの発達段階に合わせた支援方法の模索を続けるとのことです。
🧩歩行スタイルの違い=支援が必要とは限らない
歩き方に特徴があっても、日常生活に支障がなければ必ずしも支援が必要というわけではありません。しかし、以下のような問題が見られる場合は、積極的な支援が推奨されます。
✅支援が必要となるケース
- 転倒リスクが高い、または転倒が頻繁に起きる
- 好きなスポーツや遊びへの参加が難しい
- アキレス腱やふくらはぎに常に緊張がある
- 足や背中に痛みがある
これらは放置しておくと、身体活動への拒否感や運動機能のさらなる低下を招く可能性があるため、早期の対応が重要です。
🏫支援は病院だけじゃない!教室でできるアプローチとは?
支援と聞くと専門の病院や理学療法を思い浮かべがちですが、日常の生活環境で取り入れられる支援方法も存在します。
🎉 Joy of Moving Program:楽しみながら運動能力を伸ばす
ラインハート教授が開発した「Joy of Moving Program」は、学校や教室内で仲間と一緒に身体を動かすアクティビティを通じて、運動能力や協調性、自己効力感を育むプログラムです。
この取り組みによって、運動スキルの向上だけでなく、社会的なつながりや自信の向上にもつながることが確認されています。
🎭スポーツ・ダンスなどの集団活動も有効
運動スキルを支えるには、スポーツやダンスといった集団での身体活動が効果的です。
これにより以下のようなメリットが期待できます:
- モチベーションの向上(仲間と楽しく取り組める)
- 体幹やバランス感覚の自然な強化
- 自己表現の場としての活用
研究によれば、こうした活動に継続的に参加することで、自閉症の子どもたちの身体的・社会的発達が促進されるとされています。
🧒「違い」は弱点ではなく、支援のヒントになる
自閉症に伴う歩き方の違いは、単なる身体的特徴ではなく、その人の脳の働きや認知特性を反映した大切なサインです。
支援が必要かどうかを判断するためには、「歩き方」そのものではなく、**その結果として生じる困難(痛み・転倒・活動制限)**に注目することが重要です。

