乳児を激しく揺さぶることで脳に重大な損傷が生じる「揺さぶられっ子症候群(Shaken Baby Syndrome:SBS)」。児童虐待の一種とされるこの病態は、医療や司法の現場で深刻な問題として取り上げられていますが、近年ではその診断基準や科学的根拠に対しても疑問が呈されています。
本記事では、実際に自らの子どもがSBSと診断され、後にその医学的前提に疑問を抱き、徹底的な調査を行った神経科学者シリル・ロサント氏の事例を中心に、SBSにまつわる誤診や医学・司法の限界について深掘りしていきます。

🚨誤診から始まった「家族の崩壊」──ロサント氏の経験
神経科学者であるシリル・ロサント氏がこの問題に取り組むきっかけとなったのは、2016年、南フランスでの休暇中に生後5か月の息子・デイビッドくんが突然「硬膜下出血」の診断を受けたことでした。
医師から伝えられた言葉は、「これは揺さぶられっ子症候群です」というもの。児童虐待の可能性を示唆された家族は、精神的なショックだけでなく、親権の一時剥奪という法的措置にも直面しました。
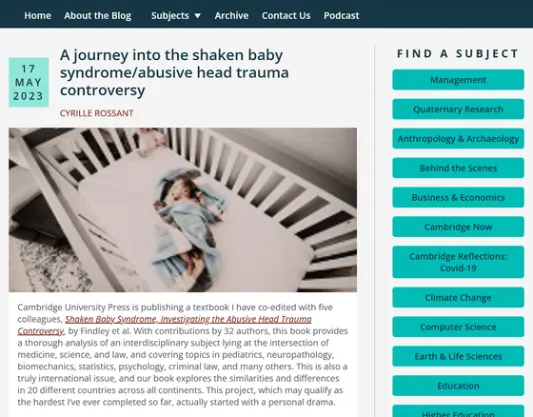
👪誰が“犯人”なのか?家族を襲った疑念と葛藤
ロサント氏自身も、妻も、そして身近な家族も「そんなことをするわけがない」と確信していましたが、医師の診断は揺るがないものでした。唯一の外部の関係者である乳母に疑念が向けられましたが、乳母も一貫して無実を主張。
一方で、別の神経小児科医は、比較的まれな「良性外水頭症」の可能性を指摘。これは頭蓋内の液体の過剰蓄積により、出血や脳への圧迫が起こる病態で、必ずしも虐待と結びつけられるものではありません。

📖医学論文500本を読み解いた父親──「揺さぶり仮説」への疑念
自ら神経科学の専門家であるロサント氏は、科学的視点からこの診断に疑問を抱き、数か月のうちに500件を超える医学論文を調査。その中で浮かび上がったのは、SBS診断の核心をなす「揺さぶり仮説」が、驚くほど脆弱な科学的根拠の上に成り立っているという事実でした。
多くの医師は、「硬膜下出血+網膜出血+骨折なし=虐待」と考えますが、実際には非外傷性の要因でも同様の症状が現れることが知られており、誤診のリスクは極めて高いのです。

⚖️医学的判断がもたらす法的な悲劇
医師によるSBS診断は、そのまま警察・検察・司法の判断材料となります。実際、世界中で年間数千人の子どもがこの仮説をもとに親と引き離され、多くの親が起訴・有罪判決を受けています。
ロサント氏の家族は、有能な弁護士の助けにより、2か月以内に親権を回復しましたが、病状が正式に外水頭症と認定されるまでには4年という歳月がかかりました。その間、乳母は生計を断たれ、ロサント家族との接触も禁じられていたのです。

🧪揺さぶられっ子症候群に関する新たな視点
SBSの診断に対する批判は少しずつ医学界にも広まりつつあります。実際、以下のような事実が報告されています。
- 🧬 遺伝性疾患、代謝障害、感染症などが同様の症状を引き起こす場合がある
- 🩸 転倒やごく軽微な外傷でも、脆弱な乳児には深刻な結果をもたらす可能性がある
- 👁️🗨️ 網膜出血や硬膜下出血の「唯一の原因が揺さぶり」とは限らない
そして最も深刻な問題は、「証拠がないにもかかわらず、医学的所見だけで起訴されてしまう」構造です。
🔍誤診の連鎖を断ち切るには?医療と司法の再検証が必要
ロサント氏は、こうした誤診によって多くの家族が理不尽な目に遭っているとし、以下のような提言を行っています。
- 医師がSBSを断定的に診断する前に、代替的な病因の可能性を慎重に検討すること
- 裁判所が医学的意見に頼りすぎず、客観的証拠の存在を重視すること
- 法医学の分野における「フィードバックループ」の欠如を補うため、診断や判決後の継続的な検証体制を構築すること
💡まとめ:科学に基づいた冷静な判断こそが、家族を守る鍵
揺さぶられっ子症候群は確かに深刻な問題であり、子どもを守るために早急な対応が必要なケースも多々あります。しかし、その診断が科学的に不確かであるにもかかわらず、法的判断に直結してしまう現状には重大な懸念が残ります。
「赤ちゃんの健康を守る」ためには、医学と司法の両輪が、より冷静かつ多角的な視点からSBSと向き合う必要があります。

