
❌「食べるな、動け」は効果がないどころか逆効果に?
肥満の人に最も多く向けられるアドバイスの一つが「もっと食べる量を減らして、運動を増やしてください」です。しかし、このシンプルな助言がほとんど効果をもたらさないどころか、時に有害ですらあると、イギリス・シェフィールド大学の栄養学上級講師ルーシー・ニールド氏らが指摘しています。
彼女たちは、肥満は「意志力の欠如」や「自制心の弱さ」といった個人の問題ではなく、複雑で慢性的な再発性疾患であると定義しています。事実、イングランドでは成人の約26.5%、子どもの22.1%が肥満の影響を受けており、国家全体での経済的損失は年間1,260億ポンド(約18兆円)にも上るのです。
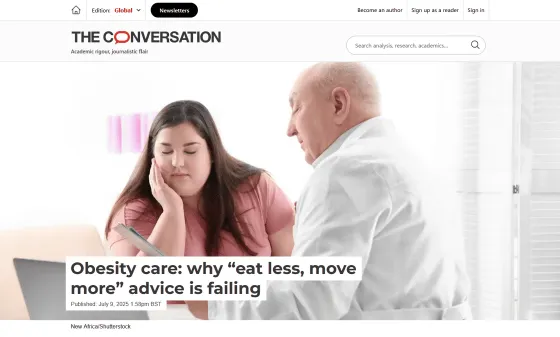
📉 肥満による経済損失の内訳(英政府試算)
| 項目 | 年間損失額 |
|---|---|
| 生活の質低下・早期死亡 | 714億ポンド |
| 医療費(NHS) | 126億ポンド |
| 雇用損失 | 121億ポンド |
| 非公式ケア(家族の介護など) | 105億ポンド |
🚨将来的には2035年に1500億ポンド(約22兆円)規模に膨れ上がると予測されています。

🧠 肥満は「環境病」であり、「個人の責任」ではない
近年の研究では、肥満の原因は以下のような多因子要素が複雑に絡んでいるとされています:
- 遺伝やホルモンバランス
- 幼少期の経験と食文化
- 精神的ストレスやうつ
- 経済的困難
- 住環境と食料アクセス
- 仕事環境や余暇活動の変化
ニールド氏らは、これらの要因が合わさることで、「肥満になってしまう環境」に人々がさらされていると主張しています。
例えば、加工食品が安価で容易に手に入り、歩かずに車で移動し、仕事や娯楽の多くがスクリーンの前で完結する生活様式こそが、肥満を引き起こす環境的要因です。

🏙️ 貧困地域ほど「肥満を助長する構造」に取り込まれやすい
低所得地域に住む人々は、安価で栄養価の高い食品にアクセスしづらく、近所に運動できる公園も少なく、スーパーまでの公共交通も不十分です。このような環境では、「太るのは個人のせい」とは言い切れない状況があります。
✅「体重増加は異常な人間の反応ではなく、異常な環境に対する正常な生理反応である」と研究チームは述べています。

🚫「意志力信仰」による社会的偏見の危険性
「自己責任」の論調に偏りすぎると、以下のような社会的弊害が生まれます:
- 肥満者に対する差別や偏見の強化
- 医療現場での不適切な扱い
- 学校や職場でのいじめや排除
- 患者自身の自己否定と孤立
つまり、間違った前提に基づくアドバイスが、社会全体の理解や支援体制を妨げているのです。
✅ 肥満対策に必要な「4つの改革提案」
ニールド氏らは、肥満問題に真摯に向き合うために、以下の4つの対策を提案しています。
1️⃣ 肥満を「慢性疾患」として扱うこと
糖尿病やうつ病と同様に、短期的な対処ではなく長期的・継続的な支援が必要です。
2️⃣ 体重に関する偏見の是正
医療現場や社会全体での「肥満差別」をなくすため、専門家の言葉選びや態度にも教育が必要です。
3️⃣ 個別化された多面的支援
治療はテンプレート化せず、心理・文化・経済状況に応じたパーソナライズドアプローチが鍵。
4️⃣ 環境と政策への投資
食のアクセスや運動機会を公平に確保し、**「健康になりやすい社会構造」**を整えることが最優先です。
🔚 結論:肥満対策の主戦場は「個人」ではなく「社会」にある
食べ過ぎや運動不足を個人の弱さとして責める時代は終わりです。現代の肥満問題は、食・都市・文化・経済という多面的な社会課題が絡み合った構造的問題であり、「病気」として向き合うべき対象です。
今後の肥満対策では、「より健康的な選択肢をとりやすくする社会設計」への転換が急務と言えるでしょう。

