「落ち着きがない」「集中が続かない」という特徴は、現代社会ではマイナス面として語られがちです。しかし最新の研究では、こうしたADHD(注意欠陥・多動性障害)的な特性が、人類の進化過程で狩猟採集生活において有利に働いた可能性が示されています。
この記事では、ペニンシュラ大学の神経科学者デビッド・バラック氏らによる興味深い研究をもとに、ADHDの進化的な側面と現代での活かし方を解説します。

ADHDとは?特徴と背景 🧠
ADHDは、注意の持続が難しい、衝動的な行動をとる、順序立てた行動が苦手といった特徴が現れる発達特性の一種です。
医学的には精神疾患として分類されますが、発症要因は完全には解明されていないのが現状です。
また、家族内で発症が見られることから、遺伝的な要素も関与していると考えられています。
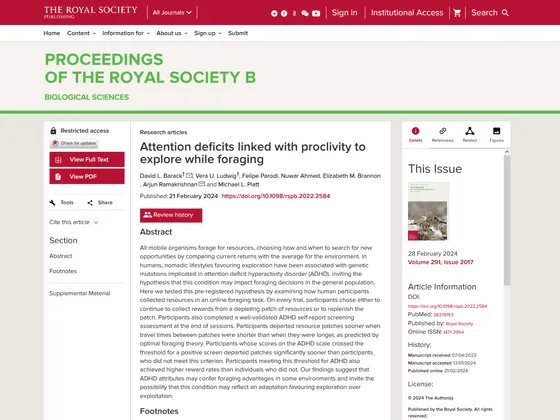
研究概要:オンライン「採集ゲーム」で能力を検証 🎮
バラック氏らの研究チームは、ADHDの特徴が狩猟採集に有利かどうかを確かめるため、506人の被験者を対象にオンラインゲームを用いた実験を実施しました。
- ルール:8分間でできるだけ多くのベリーを集める
- 選択肢:
- 同じ茂みで採集を続ける(時間効率は良いが収穫量は徐々に減少)
- 新しい茂みに移動する(移動時間のロスはあるが、多く採れる可能性あり)
実験前には、被験者に**「集中力が長続きしないか」「落ち着きがないと指摘されたことがあるか」**といったアンケートを行い、ADHD的傾向を評価しました。
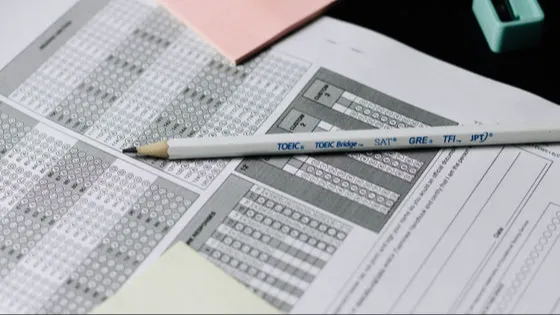
実験結果:ADHD傾向がある人は収穫量が多かった 📊
結果は驚くべきものでした。
- 同じ茂みにとどまる時間:ADHD傾向あり → 平均4秒短い
- 最終的な収穫量:
- ADHD傾向なし → 平均521個
- ADHD傾向あり → 平均602個
つまり、ADHD傾向がある被験者は「早めに見切りをつけて新しい資源を探す」行動をとる傾向があり、その結果として収穫総量が約15%増加しました。
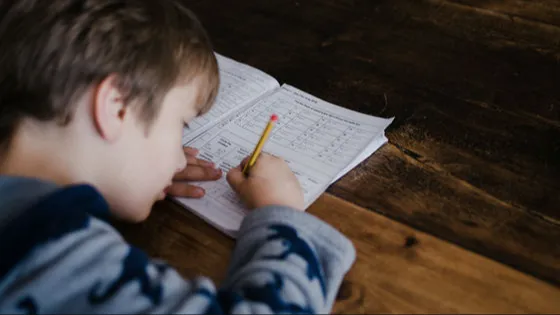
進化的視点:なぜこの特徴が有利だったのか? 🏹
人類や類人猿は賢い採餌者でありながらも、同じ場所で資源を採り続けてしまい、結果的に乱獲を招くことがあります。
しかし、ADHD的な衝動性や探求心は、資源枯渇前に移動する行動を促すため、長期的には生存に有利だった可能性があります。
バラック氏は、「この特徴は初期の狩猟採集民の資源管理において重要な役割を果たしたかもしれない」と述べています。
現代社会での活かし方 💡
現代では狩猟採集はほとんど行われていませんが、情報探索や学習、ビジネスにおいても同様の意思決定プロセスが存在します。
例:試験勉強の場合
- ADHD傾向がある人 → 「役に立たない教材」と判断すると早く切り替え、別の情報源を探す
- ADHD傾向がない人 → 同じ教材を使い続ける傾向が強い
この「素早い切り替え」が、情報過多の現代ではむしろ効率的な戦略になる場合があります。
専門家の評価 🗣️
ワシントン大学の神経科学者ダン・アイゼンバーグ氏は、「ADHD的特徴のある人とない人では採集戦略に明確な違いがある」と高く評価。
ただし、過去の環境でどの程度適応的だったかの判断は難しいとしつつも、この研究は神経多様性(ニューロダイバーシティ)の価値を再認識させるものだと述べています。
まとめ:ADHDは「欠点」だけではない
- ADHD的特徴は、過去の狩猟採集生活で資源確保に有利だった可能性
- 現代でも「切り替えの早さ」が情報収集や学習に有効
- 特性を理解し、環境に合わせた活用が重要
ADHDを単なる「障害」として捉えるのではなく、環境次第で強みになる特性として認識することが、本人の可能性を広げる第一歩となります。


