「子どもにスマホを持たせるのは早すぎる?」「SNSが悪影響を及ぼすのでは?」
そんな疑問を抱く保護者の方に朗報です。米サウスフロリダ大学の研究チームが実施した大規模調査「Life In Media Survey」により、スマートフォンが子どもにもたらすポジティブな影響が明らかになりました。
✅ 調査の概要:11~13歳の1500人超を対象に追跡調査
この調査は、米フロリダ州在住の11~13歳の子どもたち1500人以上を対象に、スマホなどのデジタルメディア使用と幸福度の関係を分析したもの。将来的な長期追跡研究(最大25年にわたる予定)にも発展する予定で、信頼性の高い調査となっています。

☀️ スマホ所有が子どもの幸福度を高めるという結果に!
調査によると、スマートフォンを所有している子どもは、持っていない子どもよりも幸福度が高い傾向が見られました。
- うつ症状や不安を感じる割合が低い
- 友人との直接的な関わりが多い
- 自己肯定感が高い
また、スマホを持っている子どもは社会性にも優れ、精神的に安定していることがわかりました。研究チームは、「スマートフォンの所有は、想定されていたほど有害ではなく、むしろ有益な場合が多い」と結論づけています。
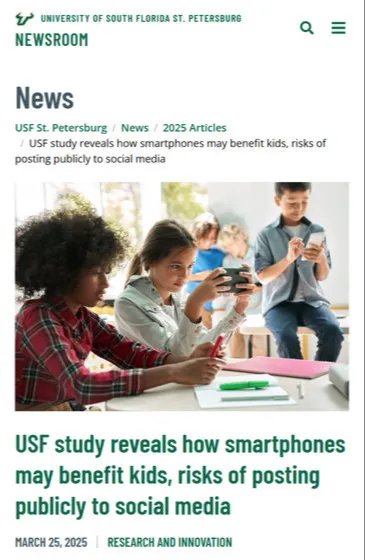
🕒 使用時間の制限はあまり意味がない?
興味深いことに、「スマホやPCの利用時間を制限することは効果がない」との結果も出ています。
- 11歳の70%以上がすでにスマホを所有
- 多くは8歳半までに入手している
- 利用時間の制限は、子どもにとってストレスになることも
過去の研究でも、スクリーンタイムの長さが直接的に幸福度に影響するとは限らないとされており、使用方法の中身がより重要とされています。
⚠️ SNS投稿には要注意!精神面への影響が大きい
一方で注意が必要なのが「ソーシャルメディアへの投稿」です。頻繁に投稿する子どもたちには、以下のようなリスクが指摘されています。
📉 中度〜重度のうつ症状
📉 不安障害のリスク
😴 睡眠障害(投稿が多いほど睡眠時間が減少)
SNSは簡単に「見られること」や「評価されること」と結びつきやすく、ストレスや自己否定感の原因になる可能性があります。

🚨 ネットいじめの影響も深刻
ネット上でのちょっとした言葉の暴力も、子どもにとっては大きな傷になります。
- 調査対象の60%が過去3カ月以内にネットいじめを経験
- 被害を受けた子どもは、
- 落ち込み(32% vs 11%)
- 怒り・かんしゃく(36% vs 10%)
- テクノロジー依存の傾向(64% vs 45%)
ネットいじめの影響は、メンタル面だけでなく、依存傾向の悪化にも直結していることがわかります。
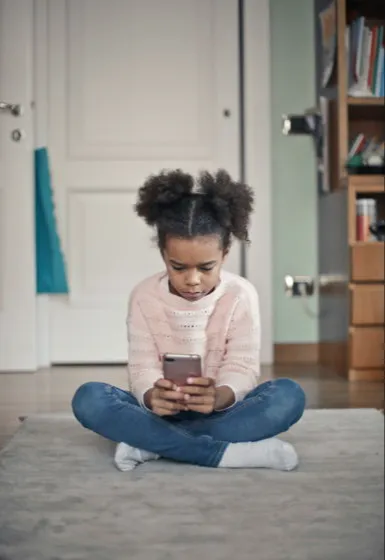
🛌 スマホは寝室に持ち込まないのがベター
睡眠とスマホの関係についても重要なポイントが示されました。
- スマホをベッドに置く子の平均睡眠時間:8.6時間
- 別の部屋に置く子の平均睡眠時間:9.3時間
寝室にスマホがあることで、通知音や誘惑で睡眠の質が落ちるケースも。子どもには「スマホを別の部屋に置く習慣」をつけさせることが大切です。

👨👩👧👦 研究チームからの3つの推奨事項
サウスフロリダ大学の研究チームは、親や教育関係者に向けて以下の3つのアドバイスを示しています。
1️⃣ 11歳でスマホを持たせることは有害ではなく、有益である可能性が高い
2️⃣ SNSへの投稿は控えめに。ネットいじめの兆候にはすぐに対応を
3️⃣ 寝室でのスマホ使用は避け、良質な睡眠を確保する
🔍 今後の研究にも注目!生涯を通じた影響を解明へ
この調査は序章にすぎません。研究チームは、今後25年間にわたり約8000人の子どもを対象にした追跡調査を予定しており、以下のような長期的な影響を解き明かしていく方針です。
- 📱 長時間のスマホ使用が視力や脳に与える影響
- 🧠 幼少期のSNS体験が30歳時の性格や人間関係に与える影響
- 😌 幸福度・社会性との関連
このような長期研究は、親や教育者、医療関係者にとって極めて貴重なガイドラインになるでしょう。
📝 まとめ:スマホ=悪ではない、正しく使えば子どもの味方に!
今回の研究が示すように、スマホの所有そのものが子どもに悪影響を与えるとは限りません。
むしろ、使い方次第で社会性・幸福度・自己肯定感を高めるツールにもなり得ます。
ただし、SNS投稿や寝室での使用には注意が必要。保護者は「使いすぎを叱る」のではなく、「どう使うかを共に考える姿勢」が求められます。


コメント