感染症予防に広く用いられてきた抗生物質「ペニシリン」。とりわけ化膿レンサ球菌(A群β溶血性レンサ球菌)に対する治療では、1950年代に定められた「1ミリリットルあたり20ナノグラム」という黄金比が長年守られてきました。
しかしこのたび、オーストラリアの研究チームが人に菌をあえて感染させるという画期的な試験を実施し、この基準が「過剰投与だった可能性」が示唆されました。

🦠化膿レンサ球菌とは?──のどの痛みから重篤な合併症まで
化膿レンサ球菌は、のどの痛み(咽頭炎)や発熱、さらには急性リウマチ熱、腎障害、心不全といった重い合併症を引き起こす危険な細菌です。特にリウマチ性心疾患のリスクが高いため、感染既往のある患者は、月1回の筋肉注射で「ベンザチンベンジルペニシリン」を10年以上にわたって継続投与されることもあります。
この治療法は非常に痛みを伴い、多くの患者が継続を断念してしまう現実がありました。
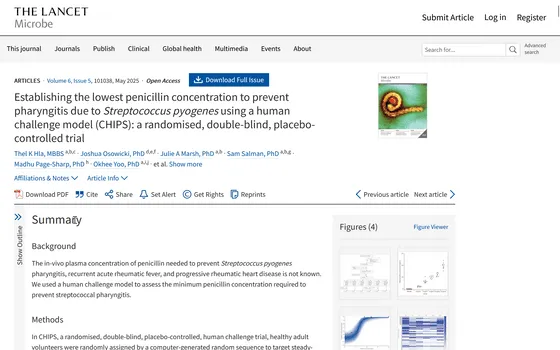
🧪人間への「意図的感染」で得られた新知見とは?
西オーストラリア大学および感染症研究機関の研究者たちは、思い切ったアプローチに踏み切りました。健康な被験者に化膿レンサ球菌を意図的に感染させ、「どれくらいのペニシリン濃度で再感染を防げるか」を精密に検証したのです。
その結果、感染予防に必要なペニシリン濃度はこれまでの半分以下──「1ミリリットルあたりわずか8.1ナノグラム」で十分であると判明しました。従来の“20ナノグラム”という基準が、実は過剰だった可能性があるのです。
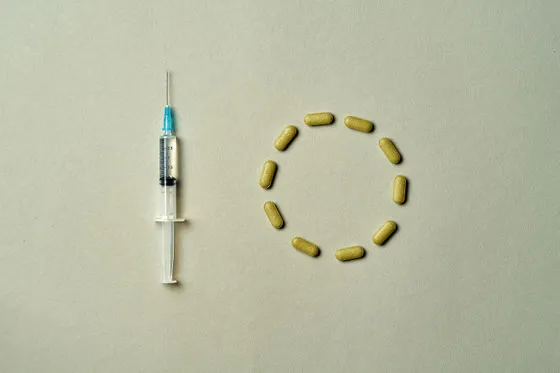
💡「より少なく、より痛みなく」──治療法の革新へ
この成果により、今後はより低用量・低痛性の投与方法の開発が現実味を帯びてきました。筋肉注射から、より痛みの少ない皮下注射への移行や、3カ月に1回で済む長時間作用型の製剤開発が進められる見込みです。
研究チームを率いたローレンス・マニング氏は「この新たな基準が臨床現場で採用されれば、患者の負担を大幅に軽減できる」とコメントしています。

👥被験者は安全だったのか?──倫理面への配慮も
本研究には60名が参加し、そのうち57名が最大5日間の入院および後日評価を完了しました。試験中に体調を崩して中止したのはわずか2名であり、倫理的にも厳密な管理体制のもと実施されたことが報告されています。
研究チームは、今後さらに多くの被験者による検証を重ねることで、この新たな治療指針を確立していくとしています。
🔍なぜこれまで「過剰な投与」が続いていたのか?
1950年代の医療技術では、ペニシリンの血中濃度や効果を正確に測定する手段が限られていたため、「安全を見込んで多めに投与する」という判断が取られていた可能性があります。
しかしその“常識”が長年見直されることなく踏襲されてきた結果、患者の身体的・精神的な負担が膨らんでいたのです。
🧭今後の展望──個別化医療と感染症治療の進化へ
今回の研究は、個々の患者にとって本当に必要な薬剤量を「科学的に見直す」大きな一歩です。感染症の分野では、安全性を損なうことなく薬剤の最適化を図る動きが今後さらに加速するでしょう。
医療の進化は、こうした“過去の前提を疑う”姿勢から生まれるのかもしれません。

