🔍 一般認識とは違う?「燃え尽き症候群=仕事」の常識に再考を促す最新研究
「バーンアウト(燃え尽き症候群)」と聞くと、多くの人が長時間労働や厳しい職場環境を思い浮かべるのではないでしょうか。実際、世界保健機関(WHO)もこの症状を「職業上のストレスによる現象」と定義しています。
しかし、ノルウェー科学技術大学の研究チームが発表した最新の調査では、燃え尽き症候群の原因は仕事以外にあることが多いという意外な実態が明らかになりました。

📊 調査内容:813人に聞いた“バーンアウトの本当の原因”
- 対象:ノルウェー人の働く成人813名(女性70.5%)
- 年齢層:18〜34歳が最多(38.5%)
- 調査項目:疲労の度合い・原因の自覚・生活背景など
結果として、「燃え尽き症候群の原因は仕事」と回答したのはわずか27.7%。つまり、約7割以上の人が「仕事以外が原因」と認識していたのです。
🧩 例:睡眠障害、家庭内の問題、育児・介護、性格傾向(不安傾向)など
さらに、アメリカでの別調査でも64%が「仕事が原因ではない」と回答しており、国を超えて同様の傾向が見られます。
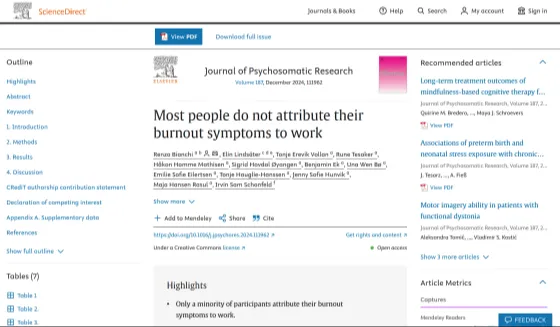
🧬 性格や私生活が“心の消耗”を生む
筆頭著者のレンゾ・ビアンキ准教授によると、**「性格特性」や「家庭の悩み」**が慢性的ストレスに直結する場合が多く、これが燃え尽き症候群につながるとのこと。
特に不安傾向が強い人は、家庭のちょっとした問題や将来への不安からも過剰にエネルギーを消耗し、本来は「仕事」とは関係のない場面で心が限界を迎えることがあるそうです。

📘 歴史をさかのぼる:「燃え尽き症候群」は元々“仕事専用”だった?
燃え尽き症候群は1970年代にアメリカの心理学者ハーバート・フロイデンバーガーが提唱しました。当時は看護師や医師などの対人援助職を主な対象とし、強い職業的ストレスを前提とした概念でした。
しかし、今回の研究チームはこの定義が現代社会においては狭すぎると指摘。ビアンキ准教授は、「そろそろ“燃え尽き症候群=仕事”という見方を見直す必要がある」と語っています。

💬 研究者の提言:「仕事に原因を求めすぎない」視点を持とう
燃え尽き症候群は確かに職場で起こることもありますが、もし原因が私生活にある場合、職場環境の改善だけでは根本的な解決には至りません。
ビアンキ准教授はこう述べています:
「やりがいのある仕事を見つけ、少しずつでもその仕事を愛する努力をしていくことが、心の健康を支える第一歩になるでしょう」
もちろん、すべての人が理想の職場を選べるわけではありません。ですが、私生活とのバランスや自分の性格特性への理解を深めることで、バーンアウト予防につながるのは確かです。
✅ 結論:燃え尽き症候群の“本当の敵”はどこにあるのか?
「仕事がつらい=燃え尽き症候群」とは限らず、ストレスの正体は意外なところに潜んでいることがこの研究からわかります。
🔄【ポイントまとめ】
- 仕事原因は3割以下、7割以上は私生活などが原因
- 睡眠・家庭・性格などが慢性疲労につながる
- 対処には職場改善だけでなく、生活面・性格理解も重要
今後は、ワークライフバランスの見直しだけでなく“ライフ全体のストレス構造”への理解が、燃え尽きを防ぐカギになるかもしれません。


