2025年3月、北朝鮮の金正恩総書記は、軍の情報機関「偵察総局」の傘下にAIハッキングを専門とする新たなサイバー部隊『227研究センター』の設立を命令したと報じられました。
目的はずばり、AIを駆使したハッキング技術の開発と、海外を対象とした情報戦能力の強化です。
この記事では、227研究センターの目的・役割・設立背景・採用計画などを詳しく解説し、北朝鮮のサイバー戦略にどのような変化が起きているのかを紐解きます。

🎯「227研究センター」設立の背景とは?
北朝鮮事情に詳しいニュースメディア『デイリーNK』が報じたところによると、金正恩氏は2025年2月下旬、偵察総局に対し「海外を対象とした情報戦能力を飛躍的に強化せよ」という指令を下しました。
その命令を受けて始動したのが、**AIベースのサイバー攻撃部隊「227研究センター」**です。3月9日から設立に向けた具体的な準備が進められています。
🏢センターは、偵察総局本部がある平壌市兄弟山区域の隣、万景台区域に設置されるとのこと。

🔍227研究センターの“真の任務”とは?
センターの主な任務は、情報収集というよりもむしろ攻撃的なサイバー作戦に重点が置かれています。
🛠 主な研究・開発内容:
- 🔓 外国のセキュリティネットワークを無力化する技術
- 🤖 AIを利用した情報窃取・改ざん・操作技術
- 💰 金融資産へのハッキング(仮想通貨・銀行など)
- 🧠 自動化された情報収集・分析プログラムの開発
『デイリーNK』は、「227研究センターの設立は、西側諸国のサイバー防衛網を突破し、混乱させ、経済的打撃を与えることを目的としている」と指摘しています。
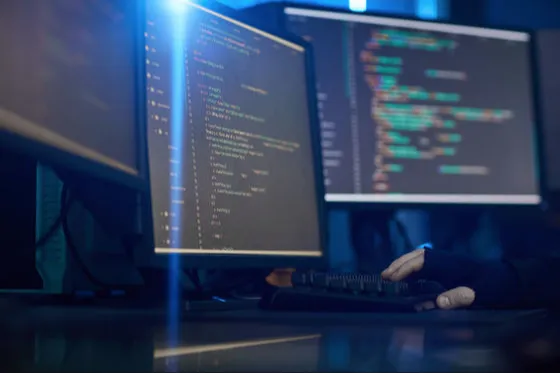
🧠AI技術を活用したサイバー戦争の最前線へ
このセンターが注力するのは、従来の人力中心のハッキングではなく、AIを使った高度で自動化された攻撃手法。具体的には以下のような動きが懸念されます。
🧩 想定されるAIサイバー兵器の特徴:
| AI技術の応用 | 目的・影響 |
|---|---|
| LLM(大規模言語モデル)の悪用 | 詐欺メール・ソーシャルエンジニアリング |
| 画像生成AI | 偽IDやなりすまし用資料の作成 |
| 自動コード生成 | 攻撃用マルウェア・ゼロデイエクスプロイトの作成 |
| ディープフェイク | 政治・軍事混乱を狙った偽情報映像の流布 |
🧨 AIの力でサイバー攻撃が「スピード・精度・拡散力」すべてで進化し、人間の対応能力を超えるリスクも。
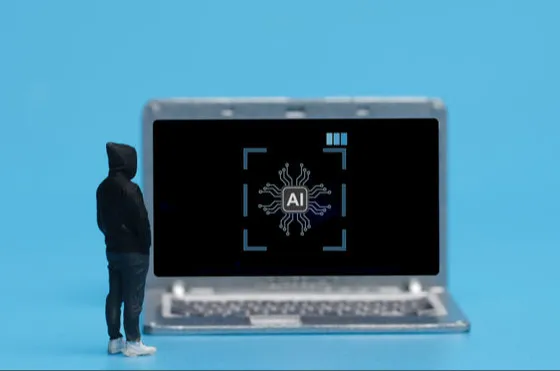
👨💻人材確保にも全力──大学卒のエリートを大量採用へ
センターでは現在、高い専門性を持つ人材の確保が急務となっており、以下のような採用計画が進行中です。
📌採用のポイント:
- コンピューターサイエンス分野で博士課程を修了または優秀な成績で大学卒業した若者がターゲット
- 約90名の人材を厳選し、24時間体制の開発部隊として運用
- 国外に展開している偵察総局の既存ハッカーグループともリアルタイムで連携
🧑🔬北朝鮮国内でAIやハッキングに長けた若手エンジニアを重点的に集め、エリート“サイバー兵団”を構築しようとしている。
⚠️227研究センターの設立が意味するものとは?
北朝鮮はすでに、以下のようなサイバー攻撃で世界を騒がせてきました:
- 💣 WannaCry(ランサムウェア)攻撃
- 🕵️♂️ 仮想通貨取引所のハッキングによる資金獲得
- 📱 Androidスパイアプリ「KoSpy」の流通(Google Play上でも発見)
- 🧠 OpenAIなどの生成AIを用いた攻撃コードの作成・詐欺メール作成の試行
- 🛰 GoogleのGeminiなど最新AIを使った情報操作も疑惑浮上中
今回の227研究センター設立により、これらの攻撃がさらに組織化・高度化・AI化する懸念が高まっています。
📝まとめ:サイバー空間における“AI冷戦”の幕開け
- 🏴 北朝鮮がAIを活用した本格的なハッキング研究機関を新設
- 🧠 情報収集よりも、攻撃型のサイバー兵器開発が主眼
- 👨🎓 国内のエリート人材を結集し、24時間体制の開発・即応体制
- 🌍 AI戦争の主戦場がサイバー空間へと移行する時代に突入
🌐サイバー攻撃は「国家の武器」となりつつあります。AIを使ったサイバー戦の脅威は、私たちの身近な生活や企業のセキュリティにも直結する重要課題です。
今後も世界中の情報機関やテック企業が、この新たなリスクにどう立ち向かうのかが注目されます。

