
2025年初頭、わずかな計算リソースで驚異的な性能を発揮するオープンソースAI「DeepSeek-R1」が登場し、世界のAI業界を揺るがしました。ところが、その後継モデルである「DeepSeek-R2」は当初予定されていた5月のリリースが実現せず、現在も登場を待ち望む声が高まっています。
遅延の背景には、中国政府がDeepSeekに対して「Huawei製チップを利用せよ」と圧力をかけたことがあると報じられています。しかし、その試みは大きな壁にぶつかり、結果として開発は難航することになりました。

DeepSeekとは?なぜ注目されているのか 🤔
DeepSeekは、中国発のAIスタートアップであり、2025年1月に発表された 推論モデル「DeepSeek-R1」 で一躍注目を浴びました。
- 最大の特徴 → 少ない計算リソースで高いパフォーマンスを実現
- トレーニングコスト → OpenAIの推論モデル「o1」のわずか約3%
- 利益率 → 理論上、1日あたり最大545%という驚異的な数値
- オープンソース化 → サーバーやローカル環境で誰でも実行可能
こうした革新性により、世界中の研究者や企業が「R1」に注目しました。🚀
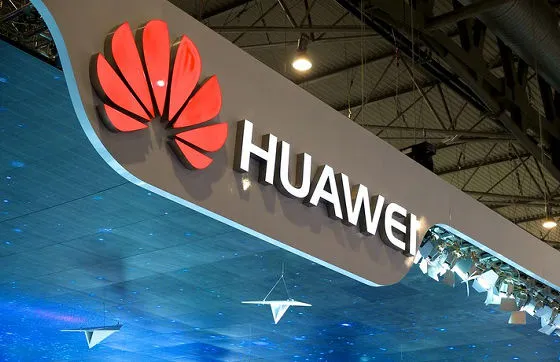
待望の「DeepSeek-R2」、なぜリリースが遅れているのか? ⏳
当初、R2は 2025年5月リリース予定 とされていました。しかし8月現在も公開されていません。その理由は、 中国政府の介入 です。
フィナンシャル・タイムズやロイターの報道によれば、中国政府はDeepSeekに対し次のような要求を出しました。
「NVIDIAではなく、Huawei製のAIチップ(Ascendシリーズ)を使って開発せよ」
その背景には、米国の輸出規制によるNVIDIA依存からの脱却や「自国技術の強化」という狙いがあるとみられます。
Huaweiチップでの開発が直面した壁 🧱
DeepSeekは政府の指示に従い、Huaweiの Ascend GPU を使ってR2の学習を試みました。
しかし結果は芳しくありませんでした。
- ⚠ パフォーマンスの不安定性
- ⚠ チップ間接続の遅延
- ⚠ ソフトウェア基盤「CANN」の制約
Huaweiはエンジニアチームを派遣して支援しましたが、最終的に 一度もトレーニング成功に至らなかった と伝えられています。
苦肉の策:「NVIDIAで学習、Huaweiで推論」 💡
最終的にDeepSeekが選んだのは、ハイブリッド方式 でした。
- 学習(トレーニング) → NVIDIA製GPUを使用
- 推論(利用時の処理) → Huawei製GPUを使用
この方法は「好み」ではなく、リソース不足と政府の意向を両立させるための「妥協策」と言われています。
Tom’s Hardwareはこのアプローチを「必要に迫られた選択」と評しました。
NVIDIA不足と中国の戦略的ジレンマ 🌀
中国国内ではNVIDIA製GPUが慢性的に不足しています。
そのため、多くの企業や研究者はHuawei製ハードウェアを利用せざるを得ません。
DeepSeekにとっても、 顧客が実際に使う環境での安定動作 を保証するため、Huawei対応は避けられないのです。
一方で、政府主導の技術自立路線は「国産化を急ぎすぎて性能が追いつかない」というリスクを浮き彫りにしました。
DeepSeek-R2の今後とAI業界への影響 🌍
DeepSeek-R2の開発遅延は、単なる企業の問題にとどまりません。
- 中国政府の介入 → 技術的自由度と開発スピードを阻害する可能性
- Huaweiの課題 → ソフト・ハードの成熟度不足が露呈
- NVIDIA依存 → 米国の規制下で中国AI産業の弱点に
一方で、R1の成功体験があることから、R2も実用段階に入れば再び大きな注目を集めることは間違いありません。💡
まとめ ✍️
- DeepSeek-R1は「低コスト・高性能」で世界を驚かせたオープンAIモデル
- R2は政府の指示によりHuaweiチップを採用 → しかし開発は失敗
- 最終的に「学習はNVIDIA・推論はHuawei」という折衷案に
- 中国の半導体戦略とNVIDIA不足が、今後のAI業界のカギに
👉 DeepSeek-R2のリリースは遅れていますが、その動向は中国のAI産業、ひいては世界のテクノロジー競争を左右する重要なテーマとなっています。

