一般的に「恥知らずであること」はネガティブに捉えられます。人前で堂々と恥ずかしい行いをすれば批判の的となり、社会的信用を失うのが普通です。
しかし、作家 ナディア・アスパルホワ氏 は2019年の時点で、「戦略的に恥知らずとして振る舞うこと」がビジネスや選挙の場で有効に機能し始めていると指摘していました

🎲 ボードゲーム「アヴァロン」が示す“恥知らず戦略”のモデル
アスパルホワ氏は、人気ボードゲーム 「レジスタンス:アヴァロン」 を例に挙げています。
これは「人狼ゲーム」に似た正義 vs 邪悪の心理戦で、正義陣営には「マーリン」という役職が存在します。
- マーリン:邪悪陣営の正体を知っているが、最後に正体を見破られると負ける
- パーシヴァル:マーリンを知ることができる「護衛役」
通常はパーシヴァルが囮となって邪悪陣営をミスリードしますが、時にマーリン自身が 「自分がマーリンだとバレるような発言をわざとする」 という戦略を取ることがあります。
👉 「こんなに愚かな発言をするわけがない、これはマーリンではなくパーシヴァルだ」と思わせることで、結果的に自分を守るのです。
つまり、あえて“恥知らず”に振る舞うことで有利に立つ戦術 です。
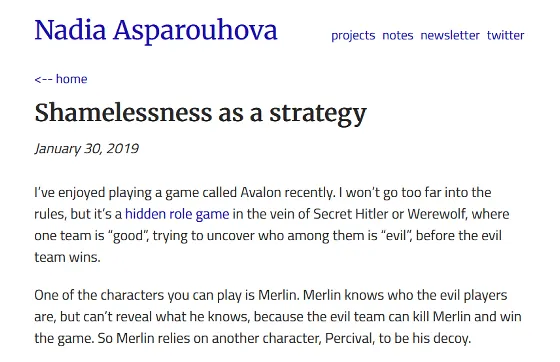
🌟 パリス・ヒルトンに見る「恥知らず戦略」の成功例
アスパルホワ氏はこの戦略を現実に広めた人物として パリス・ヒルトン氏 を挙げています。
- 2003年、リアリティ番組放送直前にスキャンダル映像が流出
- 世間の常識では大打撃になるはずが、むしろ知名度を爆発的に拡大
- 「金髪で愚かな相続人」というステレオタイプを演じることで、逆にセレブタレントとしての地位を確立
つまり「恥ずかしい」とされることを逆手に取り、注目とブランド価値を生み出した のです。

🗳️ 政治における「恥知らず戦略」 ― ドナルド・トランプ氏
この戦略は政治の世界でも見られます。
2016年のアメリカ大統領選挙では、ドナルド・トランプ氏が過激で大胆な発言を繰り返し、既存政治家から批判を浴び続けました。
しかし、結果はトランプ氏の勝利。
アスパルホワ氏は「2016年の選挙は、まったく新しい政治スタイルの幕開けだった」と振り返り、今後も“旧来のルールを守る政治家”は苦戦するだろうと予想しています。

📉 本来の「恥」の役割と現代の逆転現象
歴史的に「恥」は人を抑制し、社会の秩序を守る役割を果たしてきました。
しかし現代では次のような変化が起きています。
- 🌐 オンラインコミュニティの普及で境界線が曖昧に
- 👥 「制裁」はむしろシグナルとなり、新たな“共鳴者”を集めてしまう
- 💡 結果として、恥知らずな行動が「炎上ではなく集客」につながる
アスパルホワ氏はこれを「夜空に打ち上げられる照明弾」と例えています。
本来の制裁が、逆に“信者”を呼び寄せる道標になっているのです。
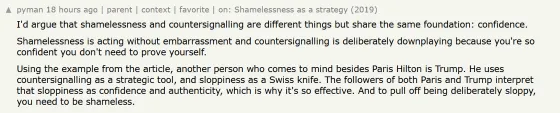
また、恥知らずに見える人が好かれるのは、人々がありのままの姿である「本物らしさ」を求めているからだという意見や、ヒルトン氏の行動も恥知らずというよりも、逆境を「自分のものにした」という感じがするとのコメントもありました。あるユーザーは、恥知らずに振る舞うという戦略を考えるには、それを取り巻くインセンティブ構造や道徳について考える必要があると指摘。
💬 Hacker Newsでの議論
ソーシャルニュースサイト Hacker News でも、このテーマは議論を呼びました。
- 👕 「大金持ちがカジュアルな服を着る」ような カウンターシグナリング に近いのでは?
- 🔎 「恥知らず」と「カウンターシグナル」は違うが、どちらも 強い自信 を示している
- 🎭 「恥知らずに見える人は“本物らしさ”を持っているから好かれる」
- 📺 リアリティ番組やSNS収益構造が「恥知らず戦略」を後押ししている
一方で、「恥知らずであることはアルコールのように人の性質を増幅し、悪影響も大きくなる」と懸念する声もあります。
✅ まとめ
- 戦略的に恥知らずに振る舞うことは、ビジネス・政治の世界で効果を発揮している
- パリス・ヒルトン氏やドナルド・トランプ氏がその成功例
- 本来「社会秩序を守る罰」であるはずの恥が、今は「拡散と支持者集めの道具」へと逆転している
- ただし、その長期的影響は未知数であり、必ずしも万人が取るべき戦略ではない
アスパルホワ氏は「誰かを『恥知らず』と一蹴する前に、その行動の背景をよく分析すべき」と呼びかけています。

