注意欠如・多動症(ADHD)の特性を持つ若者は、そうでない若者と比べて音楽との向き合い方が大きく異なる可能性があることが、新たな心理学研究で明らかになりました。
特に、勉強や運動の最中に好んで音楽を流すという傾向が顕著であり、その背景にはADHDの特性に関連した脳の“刺激欲求”が関係していると考えられています。

📊 研究の概要:ADHDのある若者はどう音楽を聴くのか?
🧠 調査対象と方法
この研究は、カナダ・モントリオール大学の心理学博士課程に在籍するケリー・アン・ラシャンス氏らの研究チームによって実施されました。
- 🎓 対象:17~34歳の若者434人
- 🖥 調査方法:オンラインアンケート
- 🧾 項目内容:
- 普段の音楽の聴取習慣
- 音楽が集中力や感情に及ぼす影響
- ADHDの症状に関する標準スクリーニング質問
被験者は回答内容に基づき、以下の2つのグループに分類されました。
- 🧩 ADHDの症状がみられるグループ
- 🧩 ADHDの症状がみられない定型発達グループ
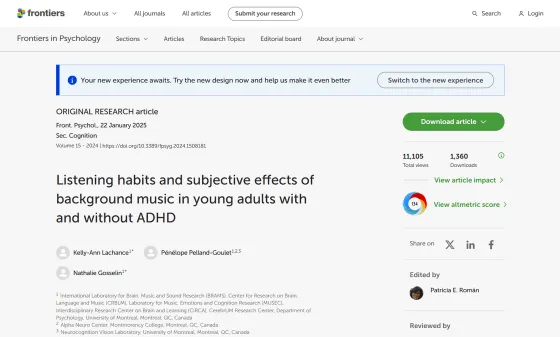
🎵 どんな場面で音楽を聴いているのか?
調査によって、若者全体が日常のさまざまな場面で音楽を活用していることが判明しました。
🧹 音楽を聴く主なタイミング:
- 📘 勉強・読書などの知的活動中
- 🏋️♀️ 運動・ワークアウト中
- 🧼 掃除・料理などの軽作業中
ただし、その中でもADHDの症状があるグループは、明確に異なる傾向を示しました。

⚡ ADHDグループの特徴的な音楽習慣
✅ よく見られた傾向:
- 🎧 学習中や運動中に音楽を聴く頻度が高い
- 🔊 刺激的な音楽(テンポが速い、音が豊かなもの)を好む
- 📈 認知負荷が低い作業中にもBGMを多用
🧘♂️ 一方で定型発達の若者は…
- 🎶 集中が必要な場面では、リラックス系の音楽を好む
- 💃 軽作業中には、刺激のある音楽を選びがち
この違いは、音楽をどのように「刺激」として活用しているかの違いを示しています。
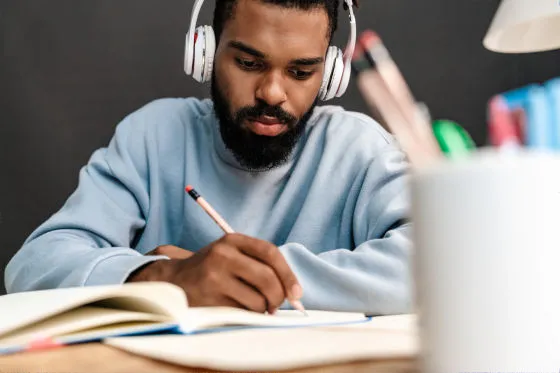
🎯 音楽は集中力や気分に影響を与える?
被験者全体の傾向として、音楽が…
- ✅ 集中力を高める
- ✅ 気分を良くする
と回答する人が多く、BGMの有用性が実感されています。
ただし、「ADHDのあるグループとないグループの間に統計的な差はなかった」とのこと。
つまり、音楽がもたらすポジティブ効果自体は、全員に共通しているようです。
🧠 「中度脳覚醒モデル」が示すADHDと音楽の関係
心理学理論のひとつである「Moderate Brain Arousal(中度脳覚醒)モデル」では、次のように説明されます:
🧬 ADHDの人の脳は、常に「覚醒レベル」がやや低い状態にある
🔊 そのため、音楽や刺激を通して自らの脳を“覚醒状態”に持っていこうとする
🎯 音楽が「自分で使える覚醒調整ツール」として機能している可能性がある
🤔 音楽はADHD対策の「セルフハック」になり得る?
研究者らは、音楽が以下のような自己調整手段になりうると述べています:
- ⚖️ 注意力のバランスをとる
- 💤 退屈感の緩和
- 🚀 認知パフォーマンスの強化
このことから、ADHD当事者が音楽を受動的に聴くものではなく、“目的をもって利用する戦略”として活用している姿が見えてきます。
🔍 今後の研究の展望
研究チームは次のような可能性に注目しています:
- 🧪 実験室での再現実験(音楽の種類と集中力の関係)
- 🎶 音楽のテンポ・ジャンルが与える具体的な影響の比較
- 📱 ADHD向けの“音楽活用アプリ”の開発や介入研究
📝 まとめ:ADHDの音楽習慣は、脳が選んだ最適な戦略?
- 🎧 ADHDのある若者は、刺激的な音楽をより頻繁に活用
- 🧠 音楽が脳の覚醒状態を調整するセルフケアになっている可能性
- 💡 すべての若者にとって、音楽は集中や感情のセルフマネジメントに役立つツール
- 🧩 今後は、音楽を活用したADHD支援の新しい手法にも期待

