「やらなきゃいけないことがあるのに、どうしても手がつかない…」
そんな“やる気の低下”や“行き詰まり”を経験したことがある人は少なくありません。
心理学的には、この状態は**「Stuck in the Middle(中間で立ち止まる)」**と呼ばれ、特に大きな目標に取り組むときに起こりやすい現象です。本記事では、その原因と解決方法を、TED-Edの解説や専門家の知見をもとにわかりやすく解説します。
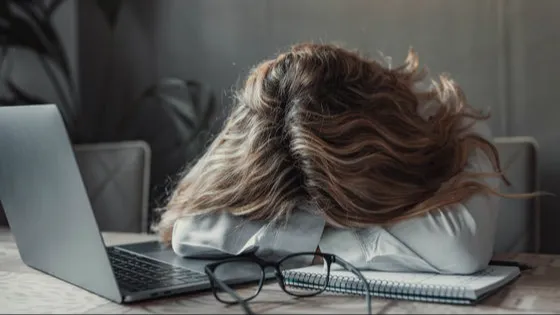
なぜ途中でやる気が落ちてしまうのか?🤔
取り組みの初期は、私たちは「スタート地点」と自分を比べ、少しの進歩でも達成感を感じます。しかし、時間が経つにつれて、視点は「最終目標」へと移行。
すると「これだけ進んだ」という満足感よりも、「まだこれだけ残っている」という焦燥感が強まり、やる気が失われていきます。
この心理的変化が「Stuck in the Middle」の正体です。特に大規模なプロジェクトや長期的な課題に取り組んでいるときに顕著に現れます。
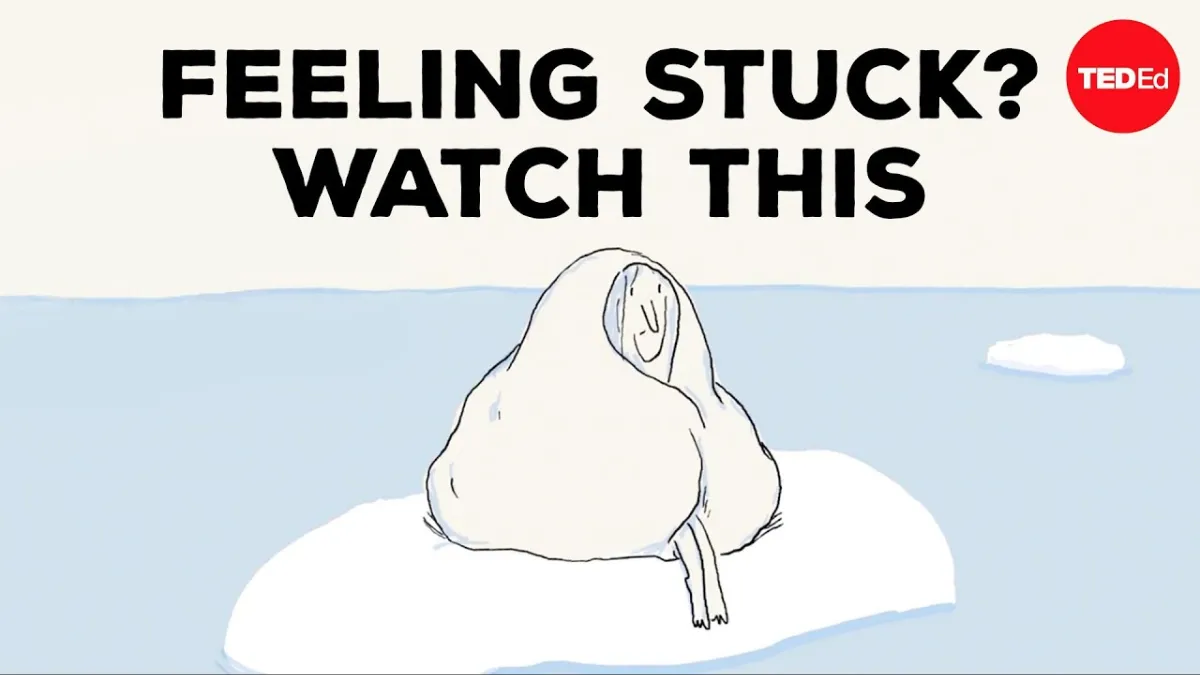
モチベーション低下を防ぐ方法
1. タスクを小さく分割する📋
- 大きな目標を小さな達成可能なサブ目標に分けることで、途中で達成感を得られます。
- 小さな成功体験の積み重ねが、継続的なやる気の源になります。
例)「本を書く」→「章ごとのアウトライン作成」→「第1章執筆」→「推敲」などに分割。

2. 感情と向き合う🧠
ダラム大学の心理学教授フーシャ・シロワ氏によると、
- そのタスクがどんな感情を引き起こしているか
- なぜ避けたいと感じるのか
を自分で評価することが大切です。不明点を明確にしたり、課題を小分けにすると心理的負担が軽くなります。

3. コミュニティの力を借りる🤝
同じ目標に向かう仲間と関わることで、以下の効果が期待できます。
- 他者の進捗や努力から刺激を受ける
- ポジティブなフィードバックをもらえる
- 行き詰まりの時に助言や励ましを得られる

タスクを分割することは、学生症候群や先延ばしクセにも効果的だと言われています。ダラム大学の心理学教授であるフーシャ・シロワ氏によると、目の前のタスクに圧倒されそうになったら一歩引いて「そのタスクがどんな感情を引き起こしたのか」「なぜそのタスクを避けたいのか」を自分で評価したり、その課題の不明な点を明確にしたり、小さな課題に分割したりすることが重要とのこと。
目標の分割は、特に大きな目標に向けて取り組む時に重要です。大規模かつ複雑な問題に取り組む場合、初めは目的意識ややりがいからモチベーションが高まりやすいもの。一方で、単一の行動やアイデアで解決できる問題はわずかであるため、最終目標に焦点を当てると無力感を抱いてモチベーションが低下してしまいやすくなります。結果として、多くの人が進歩は不可能だと考えるため、重大な社会問題などへの関心が薄まってしまいます。

TED-Edによると、大きな問題に対しても実際に行動を起こすことができる人は、「自分たちの個人的な関与が変化をもたらす可能性がある」という自信を共通して抱いているとのこと。また、社会問題の場合は、道徳的な「怒り」が役立つことも多くなっています。
4. 「怒り」や正義感を利用する🔥
社会問題や不公平な状況に対しては、「自分の行動が変化をもたらす」という信念と、道徳的な怒りが強力なモチベーション源になる場合があります。
まとめ
モチベーションが落ちるのは、意志が弱いからではなく、脳の視点の切り替わりによる自然な現象です。
解決には以下がポイントです。
- 目標を小さく分割して達成感を積み重ねる
- 自分の感情や回避理由を見つめ直す
- 仲間やコミュニティの存在を活用する
- 感情的なエネルギーを推進力に変える
日々のタスクから大きな人生目標まで、この方法はあらゆる場面で応用できます。もし今、やる気が出ないと感じているなら、まずは今日1つだけ達成できる小さなゴールを設定してみましょう✨

