同じ強さの刺激を受けても、強く痛みを感じる人もいれば、ほとんど感じない人もいます。この違いは単なる体の強さではなく、**痛みの閾値(いきち)**と呼ばれる感覚の差に関係しています。
痛みの閾値とは、熱・冷たさ・圧力などの刺激を受けて「痛い」と感じ始める境界点のことです。しかし、この閾値は単純な物理的な強度だけでなく、遺伝・ホルモン・心理状態・文化的背景など、さまざまな要因によって変化します。

👩⚕️ 性差による痛みの感じ方の違い
いくつかの研究では、女性は男性よりも痛みに敏感であることが示されています。
例えば、先進国と発展途上国を対象とした調査では、慢性疼痛の有病率が女性で45%、男性で**31%**と、明確な差が見られました。また、女性は男性よりペインクリニックを受診する割合が高い傾向があります。
この違いにはテストステロンなどのホルモンが関与している可能性がありますが、完全には解明されていません。
さらに、文化的要因として「男性は痛みに強くあるべき」という社会規範が、男性に痛みを訴えさせにくくしているケースも指摘されています。その結果、女性の方が痛みを表現しやすい傾向が生まれ、医療現場では女性患者の方が鎮痛薬を処方されにくいという不平等が生じる場合もあるのです。

⚡ 慢性痛が痛みの耐性を下げる
慢性的な痛みを抱えている人は、圧迫などの刺激に対する痛みの閾値が低くなる傾向があります。
これは慢性痛が中枢神経を過敏にし、少しの刺激でも強く痛みを感じやすくするためだと考えられています。
ただし、この低下が痛みの発症前から存在しているのか、それとも慢性痛によって引き起こされるのかは、まだ明確ではありません。

🦠 免疫系と炎症の影響
風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症では、体内に炎症が起きることで痛みの閾値が下がることがあります。
例えば、足首の捻挫などの怪我でも炎症が発生し、痛みを強く感じるようになります。氷で冷やすことが有効なのは、この炎症を抑えて閾値を回復させる効果があるためです。
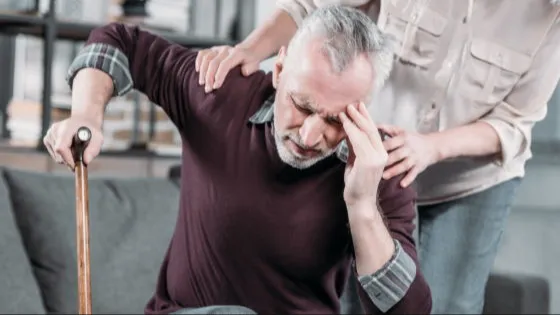
😔 心理状態が痛みに与える影響
不安・恐怖・うつ症状などの心理的要因は、痛みの耐性を下げる大きな要素です。
慢性骨盤痛の女性を対象にした研究では、精神的ストレスと痛みの強さに関連があることが分かっています。さらに、生涯で経験したトラウマが、老年期の身体的な痛みや孤独感に影響するという報告もあります。
逆に、ポジティブな心理状態やストレス軽減は痛みの感じ方を弱める可能性があり、メンタルケアが痛み対策の一部となることもあります。

🌏 文化的背景による違い
文化によっては「不快感を口にしない」「我慢が美徳」とされる場合があります。こうした環境で育つと、痛みを感じても表現しないことが習慣になり、結果として痛みへの耐性が高くなる可能性があります。
一方、痛みや不快感をオープンに共有する文化では、早期の医療介入や治療に結びつきやすくなります。
🧬 遺伝子と痛覚の関係
赤毛の人に見られるMC1R遺伝子の変異は、特定の刺激に対する痛覚を変化させることが分かっています。
例えば、熱に対しては痛みに敏感ですが、電気刺激には強いなど、刺激の種類によって反応が異なります。このメカニズムはまだ完全には解明されていません。
💡 痛みの閾値を理解する重要性
痛みの感じ方は生物学的要因・心理的要因・文化的要因が複雑に絡み合っており、医療従事者がその背景を理解することは、適切な治療につながります。
性別や人種による先入観に基づいた診断は、誤った処方や治療の遅れを招く可能性があります。
痛みの閾値を正しく理解することは、慢性痛の予防や個別化医療の実現において非常に重要です。
📌 まとめ
- 痛みの感じ方には個人差があり、遺伝・心理・文化が影響する
- 女性は男性より痛みに敏感な傾向があるが、社会規範の影響も大きい
- 慢性痛や炎症、不安やトラウマは痛みの閾値を下げる
- 文化や遺伝子も痛覚に影響を与える
- 閾値の理解は、より適切で公平な医療の実現に不可欠


