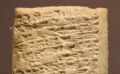― 打ち上げコスト 99 %カットの“ムーンソーラー”計画
地球―月間の物流コストは 1 kg=数百万円。
月面都市や長期探査基地を本気で造るなら、
エネルギー源すら現地調達しなければ採算が合いません。
ドイツ・ポツダム大学の研究チームが提案したのは、
月の砂=レゴリスを溶かして**“ムーンガラス”**を作り、
そこにペロブスカイト太陽電池を封入するという大胆な製造フローです。
🔬 論文:Device (Cell Press)
“Moon photovoltaics utilizing lunar regolith and halide perovskites”

1. なぜ月面でガラスを作るのか?
| 従来 | ムーンソーラー |
|---|---|
| 地球製ガラス+高効率セルを ロケットで輸送 | レゴリスを太陽光レーザーで融解→ガラス化 |
| ◎ 変換効率 30〜40 % ✕ 重く高価 | ◯ 変換効率 ~10 % ◎ 質量 0.6 %・コスト 1 % |
- 輸送重量 99.4 %減 → 発電量/打ち上げ質量は最大100倍
- レゴリス由来のムーンガラスは放射線で褐変しにくい=長寿命
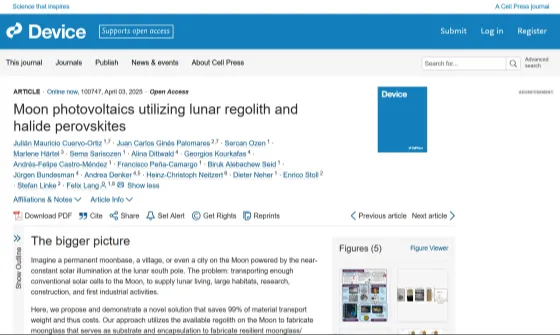
2. 研究プロトタイプのポイント
- レゴリス模擬粉末 (TUBS‑T/M)
- 高地・低地を再現した 2 種を用意
- 薄い色の TUBS‑T が最適
- 太陽光 2000 ℃ 集光炉で溶融 → ムーンガラス成形
- ペロブスカイト層をスロットダイ塗工
- 真空ラミネートで封止 = 厚みを最小化
👉 得られたセルモジュールの実変換効率 10 %
(月面大量生産でカバーできる想定)

3. 残る課題と検証ロードマップ
| 課題 | 実証プラン |
|---|---|
| 低重力・真空での溶融プロセス | 月面小型テスト炉をCLPS計画に搭載 |
| 溶剤の真空揮発 → ペロブスカイト劣化 | 無溶媒・蒸着プロセスを開発中 |
| 昼夜 300 ℃超の温度サイクル | 熱膨張マネジメント層を追加試験 |
| 電力ストレージ/送電網 | レゴリス由来固体電池・超伝導ケーブルと統合 |
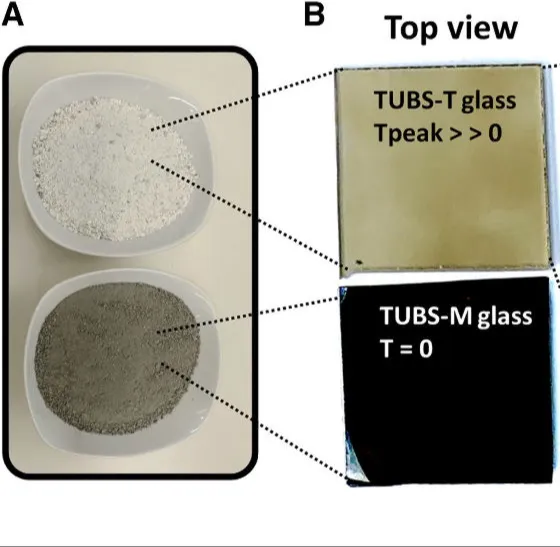
4. 月面インフラ化で得られる長期メリット
- 🚀 打ち上げ枠を科学機器や食料に振り分け
- 🏗 ISRU (In‑situ Resource Utilization) の技術基盤確立
- 🤝 将来の火星・小惑星基地でも応用可能(レゴリスはどこにでも)
🔮 まとめ:薄利多売こそ月エネルギー戦略
「効率 10 %でも 10 倍並べればいい」
ペロブスカイト×ムーンガラスは“数で殴る”発想。
輸送コストを徹底的に削り、
発電・居住・資源採取が自己完結する月面エコシステムを目指します。
次のステップは実機を月へ――。
2020年代後半のCLPS/アルテミス計画での実証に期待が高まります。 🚀

💡 参考文献・リンク
- Device, 2025 “Moon photovoltaics utilizing lunar regolith and halide perovskites”
- EurekAlert! “Solar cells made of moon dust could power future space exploration”
- Space.com “Moon dust may help astronauts power sustainable lunar cities”